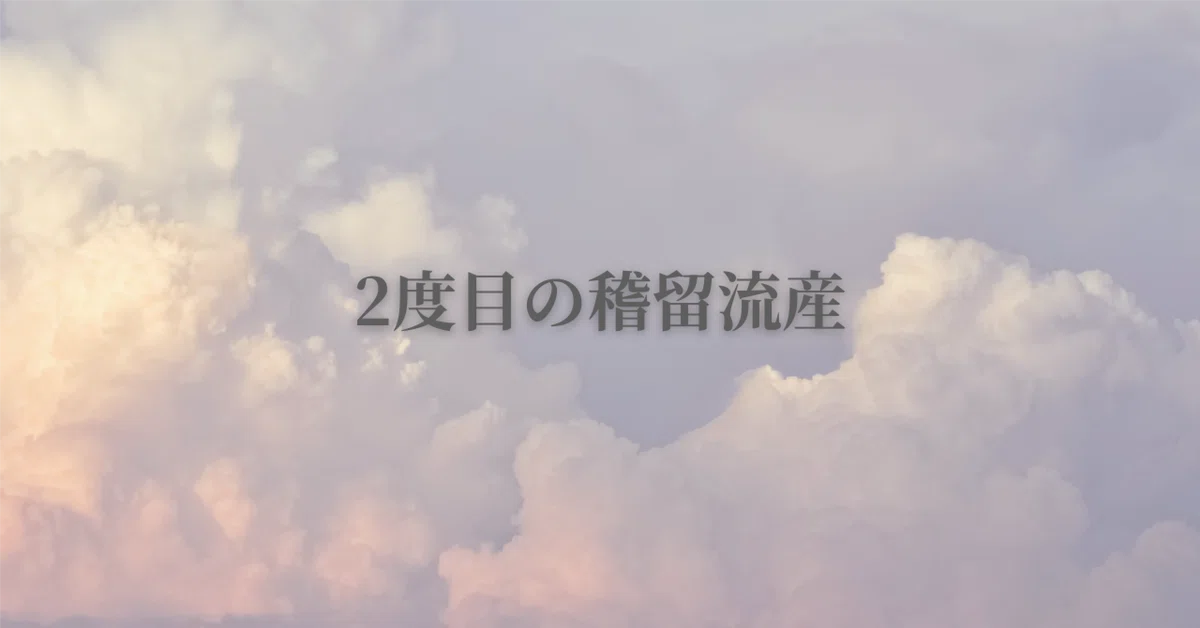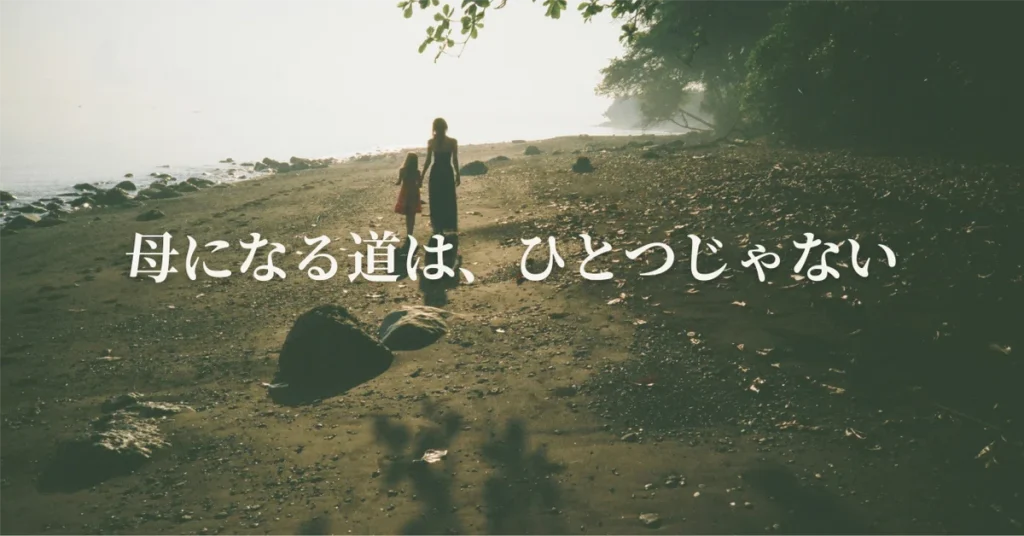「奇跡は一度きりじゃない」
そう信じていた。進み続けていた。
誰に言うでもなく、黙々と。
これは、48歳で妊娠した私が迎えた、
2度目のお別れの記録。
◆ NYへの引っ越しと奇跡の伏線
1度目の稽留流産のあと、日本の不妊治療クリニックに通い、何度か受精卵の移植を試みたが、陽性判定には至らなかった。
そうこうしているうちに、突然に主人のニューヨーク赴任が決まった。
ニューヨークは、独身時代に料理研究で1年間留学していた思い出の地。
いま振り返れば、ここにもまた、小さな奇跡の伏線が張られていたのかもしれない。
◆ アメリカで治療を再開
引っ越し後、生活が落ち着いた頃にアメリカでの治療を再開した。
どのクリニックにするか? どのドクターに託すか?
選択肢は多く、迷いながらも、カウンセリングで「この人かも」と思える相性の良いドクターに決めた。
日本と違って、アメリカでは私はなぜか「妊娠できる」という根拠のない自信があった。
◆ 未来の私への置き土産
ニューヨーク留学時代、貧乏学生だった私は、割の良いバイトを探していた。
ある日、ニューヨーク在住の日本人向けフリーペーパーをパラパラと眺めていて、「卵子提供者を求む」という広告が目に留まった。謝礼は5000ドル超。少しの不安はあったものの、それ以上に金額に目が眩んだ。
数週間悩んだ末、意を決してエージェンシーに連絡。
──が、断られた。理由は、年齢。卵子提供の条件は「20代、若ければ若いほど望ましい」。私はすでに30代だった。
その時、エージェンシーのスタッフが言った。
「提供者にはなれないけど、あなた自身のために卵子を凍結するという選択肢もありますよ」
「今すぐ子どもが欲しいわけじゃない」「子どもがいない人生も悪くない」そう思っていたはずの私が、その電話の後、卵子凍結を決めていた。断られた悔しさと、それまでには感じたことのなかった一抹の焦りが私を後押しした。
そして、数年後。結婚し、再びニューヨークに舞い戻った——私の卵子は、そこに残っていた。
◆ わずか 8 mm のハードル
きっと、スムーズにいくと思っていた。
でも、そう簡単ではなかった。
受精卵があっても、移植すれば良いというものではない。
私の場合、子宮内膜が十分な厚さにならないという問題が立ちはだかった。
赤ちゃんにとってのベッドである子宮内膜が、まるで薄いシーツのような状態。通常のホルモン療法に加え、成長因子を子宮内に注入するなど、あらゆる手を試したが、内膜はなかなか “8mmの理想” に届かない。
それでも、諦めなかった。
ニューヨークに来て6年。不妊治療歴も6年。普通なら心が折れていたはず。でも私は、「妊娠できる」という不思議な自信を、なぜか失っていなかった。いやむしろ、「妊娠できないのはおかしい」とさえ思っていた。
◆ ついに陽性!
そして、2018年の春。ようやく陽性判定が出た。
長くて、遠い道のりだった。
その頃の私は、治療と共に生きていた。生理が来たらクリニックで血液検査、薬、自己注射、移植準備。このお決まりのサイクルを何度繰り返しただろう。
お稽古事をして、友人らと会食をし、美術館に行き、さまざまなイベントに参加して、仕事も続け、ニューヨーク生活を満喫した。
でも、水面下にはいつも治療が流れていた。
◆ 日本帰国、そして——
3ヶ月に一度、日本に帰るのがささやかな楽しみだった。仕事もあるし、家族や友人にも会える。
妊娠が分かったときも、日本行きは予定通り決行。まだまだ、妊娠初期。体調はいたって普通だし、飛行機に乗るのなんて問題ない。
心配する主人をよそ目に一人で飛び立った。
日本に到着してやりたかったことの1つが、「トコちゃんの骨盤ケア教室」に参加することだった。トコちゃんとは妊婦さんがつける骨盤ケアベルトのこと。聞きかじりで、妊娠したら骨盤が緩むらしいから、しっかりケアしなきゃと息巻いていた。
48歳での妊娠。
トコちゃんベルト教室で年齢を知った先生が、笑顔でこう言った。
「希望の星です〜」
他の参加者は若いお嬢さんばかり。まるで自分の娘のような年代の人たちの中で、私は一番年上だった。でもその日、私は嬉しくて、そんなことはどうでも良かった。
2人目を妊娠中の可愛らしいママとペアを組まされ、きゃっきゃと雑談しながらトコちゃんベルトをつけたり外したりした。
・・・と、そのとき、下着にヌメっとした生温かい感覚を感じた。
冷静を装い、トイレへ。
出血だった。
翌日、病院で診察を受けた。
心拍は、消えていた。
◆ 二度目の別れ
アメリカを旅立つとき、私は妊婦だった。
帰りの飛行機では、亡骸をお腹に抱えたまま座っていた。
ニューヨークに戻った翌日、掻爬手術を受けた。
私にとって、2度目のお別れだった。
◆ 夢のあとで・・・
それでも私は、「母になる」ことを手放さなかった。
何度失っても、未来に手を伸ばしたかった。
【次回予告】
次回は、身体と心の限界を感じながらも、それでも「母になる未来」を選び続けた私の思いを綴ろうと思う。